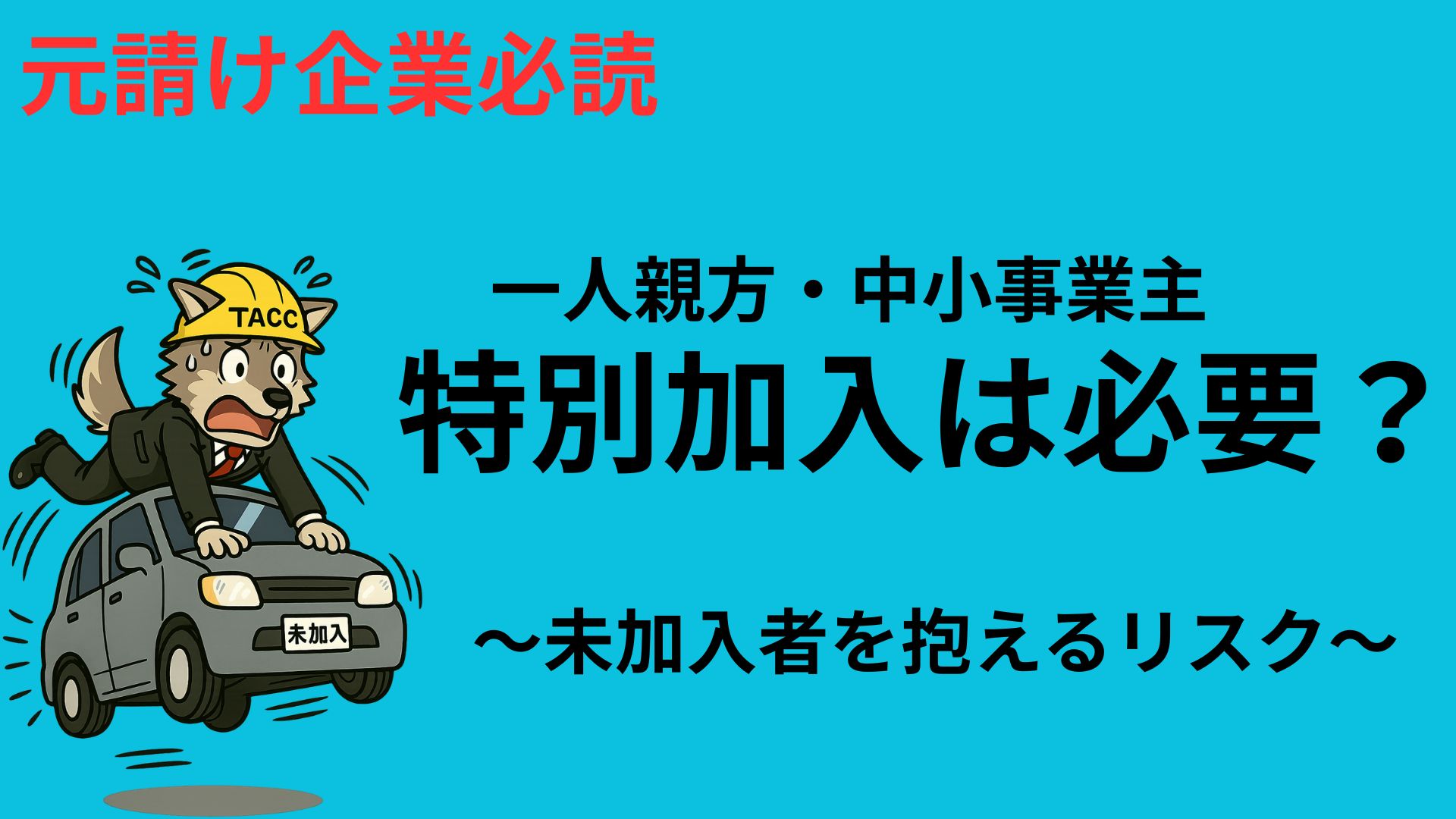はじめに
──「○○保険に加入しているから特別加入は要らない」──
そう考えている一人親方・中小事業主の方は少なくありません。
昨今ではスーパーゼネコンをはじめ、多くの元請企業が安全管理上の理由から、
「特別加入していない者は現場入場不可」とするルールを設けています。
法令で一律に義務化されているわけではありませんが、大規模現場や公共工事ではほぼ必須といえる状況です。
この記事では特別加入の必要性について解説します。
はじめに
──「○○保険に加入しているから特別加入は要らない」──
そう考えている一人親方・中小事業主の方は少なくありません。
昨今ではスーパーゼネコンをはじめ、多くの元請企業が安全管理上の理由から「特別加入していない者は現場入場不可」とするルールを設けています。
法令で一律に義務化されているわけではありませんが、大規模現場や公共工事ではほぼ必須といえる状況です。
この記事では特別加入の必要性について解説します。

下請けを抱える企業にとって必読の内容です

下請けを抱える企業にとって必読の内容です
特別加入とは?
労災保険は本来「労働者」を対象とした制度ですので、一人親方や中小企業の事業主は原則として補償の対象外となります。
しかし現場作業に従事することが多く、労働者と同じように災害リスクにさらされているため、本人や家族を守る制度として設けられたのが「労災保険の特別加入制度」 です。
特別加入は実際にどのような補償が受けれるのでしょうか
- 療養(補償)給付/療養給付
必要な治療は原則自己負担なし(労災指定医療機関等)
- 休業(補償)給付/休業給付
休業4日目から1日あたり給付基礎日額の60%+休業特別支給金20%=実質80%
- 傷病(補償)年金/傷病年金
負傷後1年6か月経過時点で治っておらず、傷病等級(1~3級)相当のときに年金(一時金併用なし)
- 障害(補償)給付/障害給付
後遺障害の等級に応じて年金(1~7級)または一時金(8~14級)+障害特別支給金
- 遺族(補償)給付/遺族給付
遺族年金または一時金+葬祭料/葬祭給付
- 介護(補償)給付/介護給付
重度の障害(常時・随時介護)に対し、実費・定額の基準で支給
特別加入によって受けられる補償は非常に幅広く、治療費から休業補償、
後遺障害や死亡時の年金、さらには介護費用まで網羅されています。
これほどまでに充実した内容を、民間の保険会社で備えることは不可能です。
「未加入者」を抱えることは自社リスクになる
特別加入をしていない一人親方や中小事業主を現場に入れて作業させるということは、例えるなら自賠責保険も任意保険にも入っていない車が公道を走っているような状態です。
もしその“無保険車”が事故を起こしたらどうなるでしょうか。
特別加入に未加入の方が労災事故に遭った場合、通常なら適用される労災保険が使えず、治療費や休業補償は一切支給されません。
しかし事故の原因が貴社にあると認められれば責任はすべて貴社が負うことになります。
重大災害や死亡事故となれば、その負担額は数千万円規模になり、
場合によっては1億円を超えることもあります。

特別加入をしていない下請けを現場に入れることは
自社経営に大きなリスクをもたらします。
対策
この現実を踏まえれば、もはや「特別加入しているかどうか」は相手任せにしてよい問題ではありません。元請・中小建設会社自身が主体的に確認し、管理すべき事項なのです。
具体的には
- 協力会社や一人親方に必ず、特別加入の加入証明書を提出してもらう
- 提出された証明書を台帳や安全書類として管理する
- 未加入者は原則として現場に入場させないルールを徹底する
こうした仕組みを整えておくことで、事故発生時のリスクを大幅に減らせるだけでなく、「安全管理が行き届いている会社」という信頼にもつながります。

特別加入は、取引継続や現場の信頼を守るための必須条件と言えます!
特別加入とは?
労災保険は本来「労働者」を対象とした制度ですので一人親方や中小企業の事業主は原則として補償の対象外となります。
しかし現場作業に従事することが多く、労働者と同じように災害リスクにさらされているため、本人や家族を守る制度として設けられたのが「労災保険の特別加入制度」 です。
特別加入は実際にどのような補償が受けれるのでしょうか
- 療養(補償)給付/療養給付
必要な治療は原則自己負担なし(労災指定医療機関等)
- 休業(補償)給付/休業給付
休業4日目から1日あたり給付基礎日額の60%+休業特別支給金20%=実質80%
- 傷病(補償)年金/傷病年金
負傷後1年6か月経過時点で治っておらず、傷病等級(1~3級)相当のときに年金(一時金併用なし)
- 障害(補償)給付/障害給付
後遺障害の等級に応じて年金(1~7級)または一時金(8~14級)+障害特別支給金
- 遺族(補償)給付/遺族給付
遺族年金または一時金+葬祭料/葬祭給付
- 介護(補償)給付/介護給付
重度の障害(常時・随時介護)に対し、実費・定額の基準で支給
特別加入によって受けられる補償は非常に幅広く、治療費から休業補償、後遺障害や死亡時の年金、さらには介護費用まで網羅されています。
これほどまでに充実した内容を、民間の保険会社で備えることは不可能です。
「未加入者」を抱えることは自社リスクになる
特別加入をしていない一人親方や中小事業主を現場に入れて作業させるということは、例えるなら自賠責保険も任意保険にも入っていない車が公道を走っているような状態です。
もしその“無保険車”が事故を起こしたらどうなるでしょうか。
特別加入に未加入の方が労災事故に遭った場合、通常なら適用される労災保険が使えず、治療費や休業補償は一切支給されません。
しかし、事故の原因が貴社にあると認められれば責任はすべて貴社が負うことになります。
重大災害や死亡事故となれば、その負担額は数千万円規模になり、場合によっては1億円を超えることもあります。

特別加入をしていない下請けを現場に入れることは自社経営に大きなリスクをもたらします。
対策
この現実を踏まえれば、もはや「特別加入しているかどうか」は相手任せにしてよい問題ではありません。元請・中小建設会社自身が主体的に確認し、管理すべき事項なのです。
具体的には
- 協力会社や一人親方に必ず、特別加入の加入証明書を提出してもらう
- 提出された証明書を台帳や安全書類として管理する
- 未加入者は原則として現場に入場させないルールを徹底する
こうした仕組みを整えておくことで、事故発生時のリスクを大幅に減らせるだけでなく、「安全管理が行き届いている会社」という信頼にもつながります。

特別加入は、取引継続や現場の信頼を守るための必須条件と言えます!